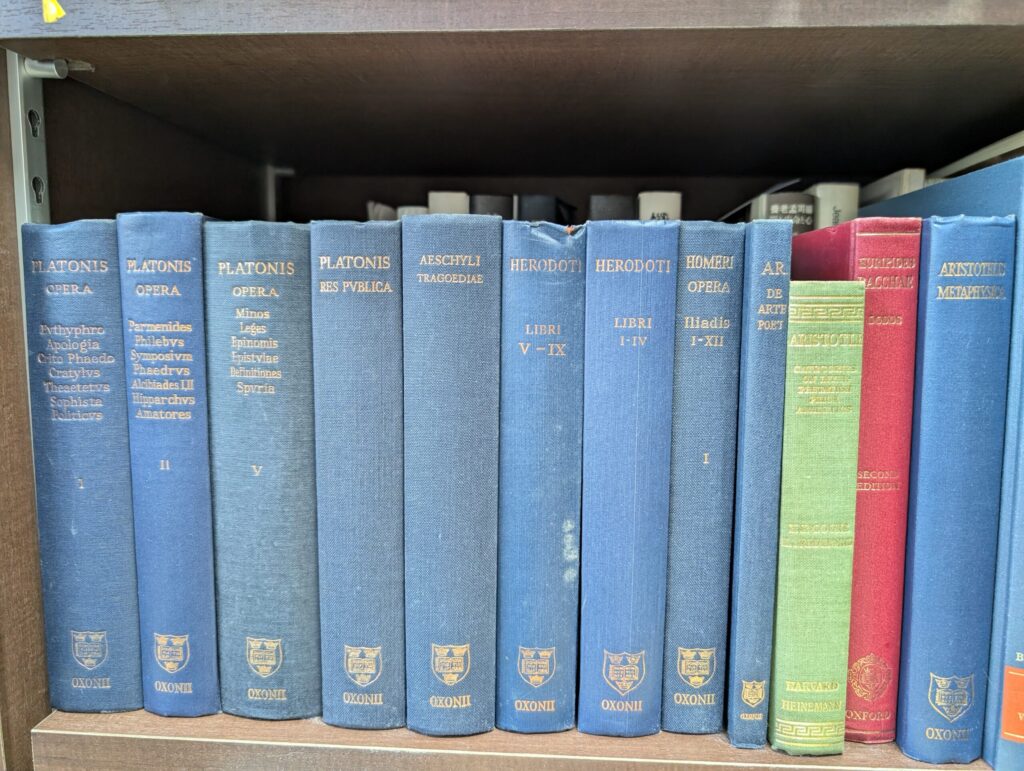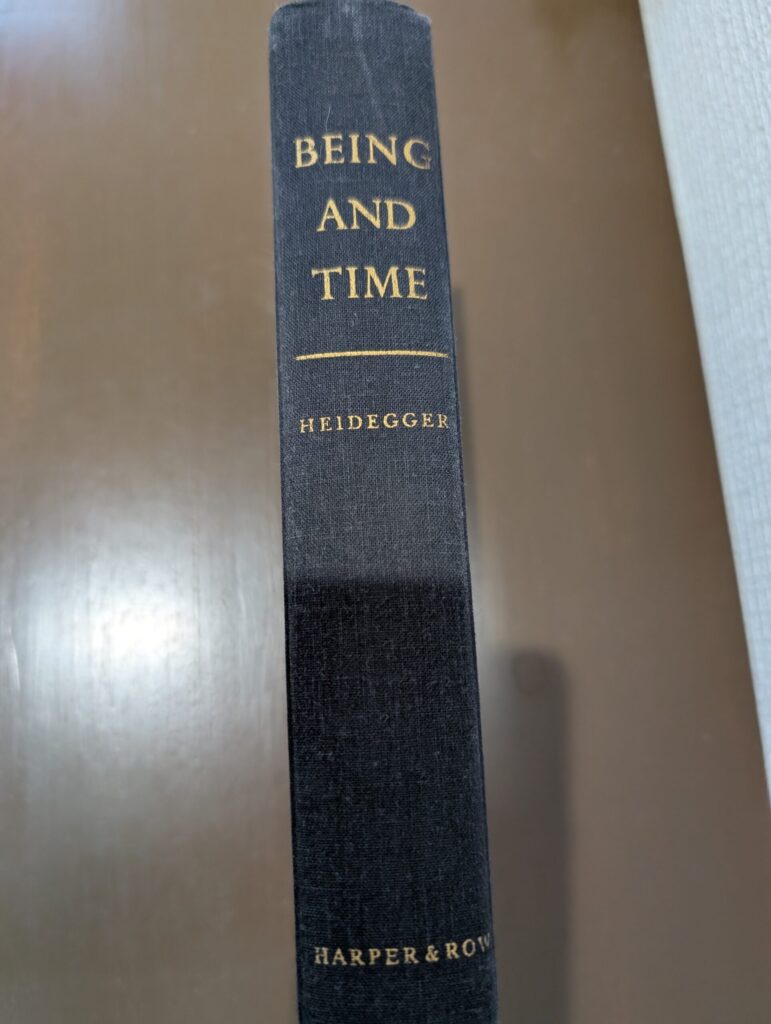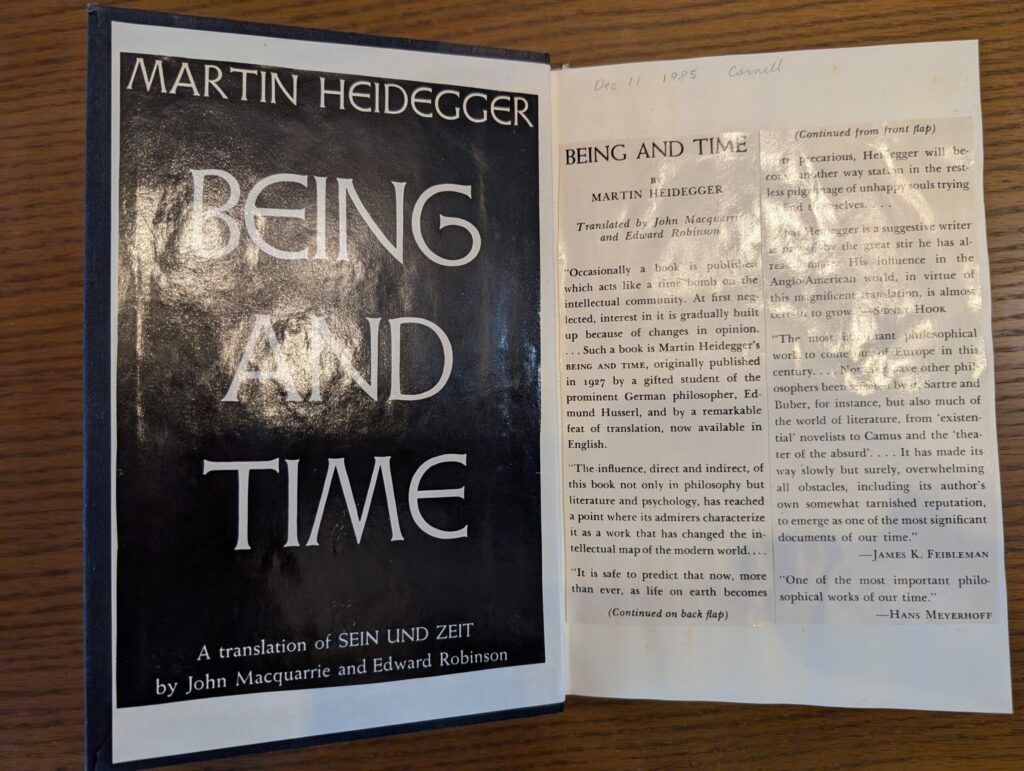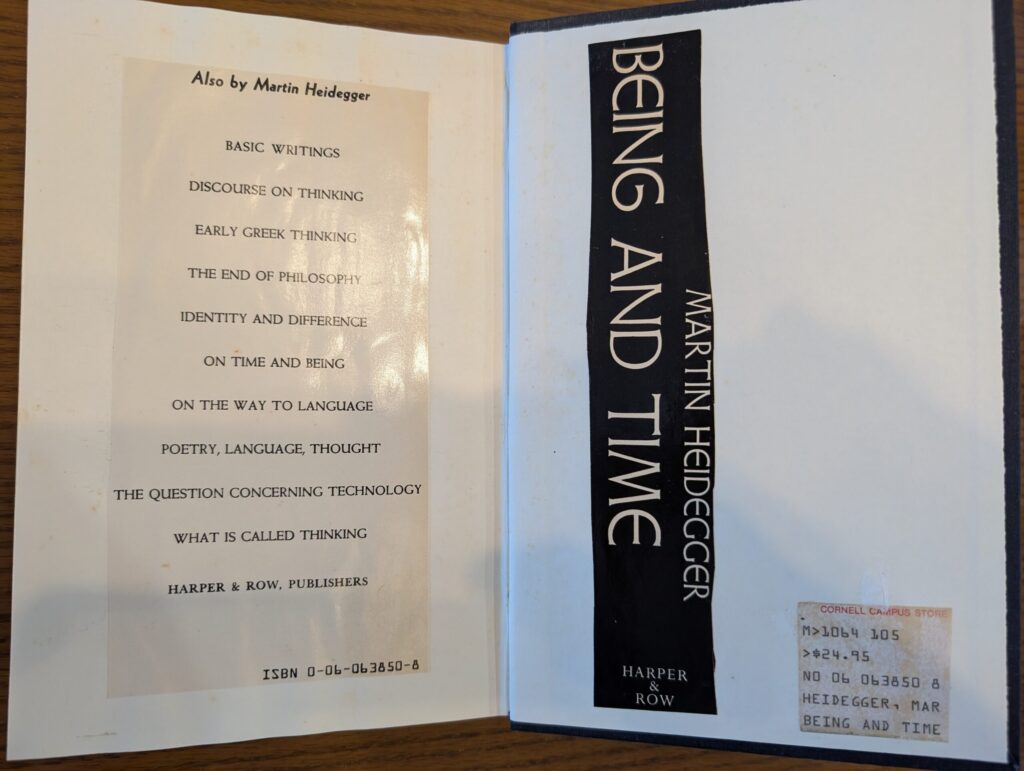「パリにて 一九五三年十月八日」
わたしは森有正をとくに専門的に研究してはいませんし、また彼について詳しい知識をもっているわけでもありません。彼の著作を全部読んだとか、ほとんど読んだというのでもありません。
しかし、わたしは森有正の著作のいくつかは真面目に、真剣に読んだことがあります。そして、彼の言葉には、忘れ難いものが本当に多いのです。今、森有正全集第1巻所収の最初のエッセイ集「バビロンの流れのほとりにて」の1ページ目をめくってみると、そこにはまず日付があります。そして、一度読んだら忘れられないような真実な響きを持った文章が始まっていきます。
「一つの生涯というものは、その過程を営む稚い日に、すでに、その本質において、残ることなく、露われているのではないたろうか。僕は現在を反省し、また幼年時代を回顧するとき、そう信じざるを得ない。」
「社会における地位やそれを支配する掟、それらへの不可避な配慮、家庭、恋愛、交友、それらから醸し出される曲折した経緯、そのほか様々なことで、この運命は覆われている。」
「暗黒のクリークに降り注ぐ豪雨、冴え渡る月夜に、遥か空高く、鳴きながら渡ってゆく一群の鳥、焼きつくような太陽の光の下に、たった一羽、濁った大河の洲にたっている鷺、嵐を孕む大空の下に、暗く、荒々しく見渡すかぎり拡がっている曠野、そういうものだけが印象に今も鮮やかにのこっている。そこには若い魂たちの辿ったあとが全部露われている。しかもかれらの姿はそこには見えないのだ。このことは僕に一つの境涯を啓いてくれる。そこには喜びもないのだ。悲しみもないのだ。叫びもなければ、呻きもないのだ。ただあらゆる形容を絶したDESOLATIONとCONSOLATIONとが、そのことが二つのものとしてではなく、ただ一つの現実として在るのだ。」
「ただたくさんのものが、静かに漲り流れる光の波を乱して、人生の軽薄さを作っているのだ。人間というものが軽薄でさえなかったら……….。」
「紗のテュールを嵌めた部屋の窓からは、昨日までの青空にひきかえて、灰色がかった雲が低く垂れ込める夕暮の暗い空が、その空の一隅かが、石畳の道の向う側にある黒ずんだ石造のアパートの屋根の上に、見える。パリの秋はもう冬のはじまりだ。」
「人間が軽薄である限り、何をしても、何を書いても、どんなに立派に見える仕事を完成しても、どんなに立派に見える人間になっても、それは虚偽にすぎないのだ。その人は水の枯れた泉のようなもので、そこからは光の波も射し出さず、他の光の波と交錯して、美しい輝きを発することもないのだ。自分の中の軽薄さを殺しつくすこと、そんなことができるものかどうか知らない。その反証ばかりを僕は毎日見ているのだから。それでも進んでゆかなければならない。」
「僕が十三歳の時、父が死んで東京の西郊にある墓地に葬られた。二月の曇った寒い日だった。」
「僕は、一週間ほどして、もう一度一人でそこに行った。」
「僕もいつかはかならずここに入るのだということを感じた。そしてその日まで、ここに入るために決定的にここにかえって来る日まで、ここから歩いて行こうと思った。」
「たくさんの問題を背負って僕は旅に立つ。この旅は、本当に、いつ果てるともしれない。ただ僕は、稚い日から、僕の中に露われていたであろう僕自身の運命に、自分自ら撞着し、そこに立つ日まで、止まらないだろう。」
(森有正(1978)森有正全集 第1巻. 筑摩書房 より抜粋)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この森有正「バビロンの流れのほとりにて」の最初の記事の日付ですが、一九五三年というのは、わたしが生まれた年です。わたしは森有正がこの記事を書いたとき、生後約半年でした。そして千葉県の田舎で両親と暮らしていました。今は、二千二十五年です。
わたしは国際基督教大学の学生だった1970年代に、森先生がキャンパスを歩いておられるのをよく見かけました。夜、教会堂でパイプオルガンの練習をされているのを、こっそり会堂に入って聞かせてもらったこともありました。一度だけ、偶然に、大学食堂でに相席になり、短い会話をさせていただいたこともありました。
今ここで、森有正の言葉について、わたしがさらに解説や説明を語る気持ちにはなれません。ただ戦争で死んでいった若者たちについて、
「そこには喜びもないのだ。悲しみもないのだ。叫びもなければ、呻きもないのだ。ただあらゆる形容を絶したDESOLATIONとCONSOLATIONとが、そのことが二つのものとしてではなく、ただ一つの現実として在るのだ。」
と書かれています。これについて、確かにそれはそうなのだと、わたし自身が少しわかるようになってきたのは、わたし自身相当の苦労をした後でした。ですから、森有正が彼の「一つの境涯」に辿り着くまで、どれほどの苦労があったのだろうか、と思うのです。